みなさんこんにちは、ゆーきゃんです。
今回のテーマは、「円安」についてです。
昨今のニュースで1ドルが135円代に突入したことをご存知の方も多いかと思います。
ニュースではその要因について語られることも多いですが、いまいちピンとこない方も多いではないでしょうか。
そこで、銀行の外国為替部門で勤務していた筆者が、「円安」の仕組みや生活への影響について解説します。
「為替レート」の決定理論と「円安」の仕組み
円安がなぜ引き起こされるかを考えるために、「為替レート」の決定理論について説明します。
説明にあたり、「スポット為替レート」の意味を確認しておきます。
「スポット為替レート」とは、取引を締結した日から2営業日後に受け渡しを行うときに適用される為替レートのことをいう。
ニュース等で報道される「為替レート」は「スポット為替レート」のことを指す。
例えば、1ドル=100円で100ドルを購入したとき、その2営業日後に
購入者は100×100=10000円を銀行に支払い、銀行は購入者に100ドルを支払います。
いま、次の状況を考えます。
①100万円を1年間\(i_{JPY}\)[%]の金利で運用する。
②100万円を現在のスポット為替レート\(S_{t}\)で全額をドルに換え、
ドルを1年間\(i_{USD}\)[%]の金利で運用し、1年後にそのときのスポット為替レート\(S_{t+1}\)で全額を日本円に換える。

①において、1年後手元のお金は\(1,000,000(1+\frac{i_{JPY}}{100})\)となります。
②において、1USD=\(S_t\)JPYで1,000,000円をドルに換えると、$\(\frac{1,000,000}{S_t}\)になります。
これを1年運用すると、$\(\frac{1,000,000}{S_t}(1+\frac{i_{USD}}{100})\)となります。
「金利平価説」の下では、
が成立するため、
$$1,000,000(1+\frac{i_{JPY}}{100})=\frac{1,000,000}{S_t}(1+\frac{i_{USD}}{100})×S_{t+1}$$
という関係式が得られます。
この関係式より、
$$S_t=\frac{100+i_{USD}}{100+i_{JPY}}×S_{t+1}…(*)$$
(*)式を考察すると、
- \(i_{JPY}\)が小さくなり、\(i_{USD}\)が大きくなる→\(S_{t}\)は上昇
- \(i_{JPY}\)が大きくなり、\(i_{USD}\)が小さくなる→\(S_{t}\)は下降
することが分かります。
また、
を意味するため、
アメリカが利上げし、日本が低金利水準を維持し続けると、「円安」の進行が予測される
ということになります。
実際の為替レートは、それ以外の要因によって厳密には金利差から導かれる為替レートとは異なりますが、その差はその決定に大きな影響を与えています。
「円安」になると何が起きる?
「円安」が起こる仕組みについて解説してきましたが、次は「円安」による生活の影響を考えてみましょう。
いま、1USD=100円から1USD=110円に円安が進行した状況を考えましょう。
例えば、パンの原材料である小麦の大部分は輸入に依存しています。
もし、小麦を10,000ドルで輸入している企業から見れば、円安によって
\(10,000×(110-100)=100,000\)円だけコストがかさむことになります。
このコストが販売価格へと転嫁され、
こととなるのです。
ですので、さまざまなものを輸入に依存している日本にとって、
ただでさえ不況なのに物価が上昇し、ますます不況が進行する事態となりかねないのです。
一方で、トヨタのような輸出がさかんな産業から見れば、円安になればなるほど儲かっていきます。
(それで儲かった企業が、給料を増やしたり、株の配当金を増やすなどして消費を促してほしいのですが・・・)
なぜ、日本銀行は「利上げ」に踏み切らないのか?
いまの議論から考えれば、
「円安」を食い止めるためには、日本も利上げすればよい
ということがいえますね。
しかし、中央銀行である日本銀行が、政策金利(日銀が市中の銀行に貸し出す際の金利)を上げてしまうとどうなるのでしょうか。
政策金利を上げてしまうと、以下のような波及効果があるため、
ただでさえ不況にある日本が、ますます不況となってしまうため、日銀は簡単に利上げに踏み切れないのです。

「指値オペ」が「悪い円安」を招く
その他の「円安」を進行させる要因について考えていきましょう。
まず、その話題に入る前に「国債」に関して説明します。
のが特徴です。
「国債」には種類があり、その償還までの期限によって、「3年債」や「10年債」などがあります。
日銀はこの「10年債」に関して、目標する金利水準を設定しています。
日銀の金融政策(物価の安定のために日銀が行う政策)の大きな柱である「イールドカーブ・コントロール」に関して、
をいいます。
日銀は「10年債」の望ましい金利水準を維持するために、
その利回りを指定して無制限の国債を買い入れ(指値オペ)
を実施しています。
日本以外の中央銀行は政策金利の利上げを行う歩調となっており、
日銀が指値で国債を購入するということは、それ以上国債の価値が下がらないことを意味します。
よって、
投資家から見れば日本国債の価値が減少する前に売却し、他の魅力的な資産への投資のために、円を売りドルを買う動きが加速する「悪い円安」が進行している
といえます。
公民の学習におすすめの参考書
公民の学習におすすめの参考書をご紹介します。
「公民」では難しい「政治・経済」に関する概念が多々出てきます。
本書は重要なポイントのみをピックアップし、確認できるようになっており非常に効率よく学習ができます。
図やイラストも豊富なので、分かりやすく、初学者の方でも無理なく取り組めます。
「とってもやさしい中学公民」で知識をインプットしたら、「完全攻略」を用いてそれをアウトプットしましょう。
本書は定期テスト対策はもちろんのこと、基礎からステップアップしてゆける構成になっているので、入試の基礎固めにも最適です。
まとめ:[中学公民]中学生でも分かる!「円安」の仕組みと生活への影響について元銀行員が分かりやすく解説!
いかがでしたか。
今回の記事では、「円安」の仕組みやそれがもたらす生活への影響について解説しました。
この内容をすべて理解できる必要はありませんが、なんとなくでも「円安」の特徴をつかんでもらえれば幸いです。
引き続き、時事ネタに関連した学習事項を解説してゆくのでお楽しみに。
最後までご一読いただきありがとうございました。
![[中学公民]中学生でも分かる!「円安」の仕組みと生活への影響について元銀行員が分かりやすく解説!](https://i0.wp.com/you-can-blog.com/wp-content/uploads/2022/06/chart-g3c32cbe89_1920.jpg?fit=1920%2C1078&ssl=1)





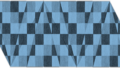





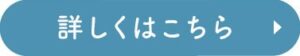
コメント