みなさんこんにちは、ゆーきゃんです。
前回は、「遺伝の計算問題」の解き方について解説しました。
今回の記事では、実際の公立高校入試で出題された問題を解説していきます。
解き方を定着させる問題演習として、挑戦してみましょう。
また、本記事と合わせて以下の記事も是非ご覧ください。
2020・沖縄・大問5
まずは、2020年の沖縄の大問5に取り組んでみましょう。
問題はこちらから参照できます。
問1の解説
純系とは、
個体群のことをいいます。
ですので、
ことになります。
いま、顕性(優性)の遺伝子が「A」で、潜性(劣性)の遺伝子が「a」ですから、
赤花の純系は「AA」で、白花の純系は「aa」となり、そのかけ合わせでできる子は「Aa」となります。
よって、答えはエと決まります。
問2の解説
問2に関しては前回の記事でも学習したように、答えは「分離の法則」です。
問3の解説
問3では、表を書いて考えていきましょう。
まず、表に、分離の法則に基づき、親の各配偶子(精細胞や卵細胞)に入る遺伝子を書いていきます。
| A | a | |
| A | ||
| a |
続いて、残りのマスに各遺伝子をかけあわせてできる「遺伝子のペア」を書いていきます。
| A | a | |
| A | AA | Aa |
| a | Aa | aa |
よって、AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1より、赤花 : 白花 = 3 : 1となります。
そのため、得られる種子の\(\frac{3}{4}\)が赤花を示す遺伝子Aをもっていることになります。
以上から実験Ⅱで得られた種子8300個のうち遺伝子Aを持つものは、\(8,300×\frac{3}{4}=6,225\)個と求まります。
答えは、エです。
問4の解説
この問いからやや難易度が上がります。
いま、Xは赤花なので、それの持つ遺伝子のペアは「AA」または「Aa」ということになります。
Xが「AA」だとすると、それと「aa」をかけあわせれば、すべて「Aa」が生じることになってしまいます。
よって、Xは「Aa」だと分かります。
ちなみに「Aa」と「aa」をかけあわせれば、以下の表が書けます。
| a | a | |
| A | Aa | Aa |
| a | aa | aa |
よって、Aa : aa = 1 : 1となり、問題の条件と合致します。
問5の解説
まず、「Aa」の自家受粉に関して問3より、孫の個体比は AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1となります。
「aa」の自家受粉からは、以下の表のとおり、孫の個体比はAA : Aa : aa = 0 : 0 : 4となります。
| a | a | |
| a | aa | aa |
| a | aa | aa |
いま、親の個体比について Aa : aa = 1 : 1なので、これら2つの比の辺々をそれぞれ足し合わせて、
AA : Aa : aa = 1 : 2 : 5となり、赤花 : 白花 = 3 : 5と求まります。
別解として次のような考え方もOKです。
「Aa」の自家受粉に関して、
- 「赤花」となる種子が生まれる確率=\(\frac{1+2}{1+2+1}=\frac{3}{4}\)
- 「白花」となる種子が生まれる確率=\(\frac{1}{1+2+1}=\frac{1}{4}\)
と考えることができます。
「aa」の自家受粉に関して、
- 「赤花」となる種子が生まれる確率=0
- 「赤花」となる種子が生まれる確率=1
と考えられます。
いま、親である「Aa」と「aa」の個体数を\(N\)とすれば、孫において、
- 「赤花」となる種子の数の期待値=\(N×\frac{3}{4}\)
- 「白花」となる種子の数の期待値=\(N×\frac{1}{4}+N×1=N×\frac{5}{4}\)
よって、赤花 : 白花 = \(N×\frac{3}{4}\) : \(N×\frac{5}{4}\) = 3 : 5
となります。
2020・奈良・大問3
続いて、2020年の奈良県の大問3に挑戦してみましょう。
問題はこちらから参照できます。
(1)の解説
答えは、精細胞です。
花粉に含まれる精細胞が、めしべ内の卵細胞と受精します。
(2)の解説
これは繰り返しになりますが、孫の個体比 AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1となるのでした。
よって、孫で生じる赤花を示す遺伝子の組み合わせは「AA」と「Aa」です。
(3)の解説
まず、①と③のかけあわせに注目しましょう。
「Aa」同士を掛け合わせると、AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1の比率で子孫ができるため、
丸 : しわ = 3 : 1ですから、①と③は「Aa」と決まります。
次に、①と②のかけあわせに注目します。
①は「Aa」ですから、②が「aa」あるいは「Aa」だと、「aa」が生まれることになってしまいます。
よって、②は「AA」しかあり得ないことになります。
ちなみに、「Aa」と「AA」をかけあわせると以下のようになり、子孫はすべて赤花となります。
| A | A | |
| A | AA | AA |
| a | Aa | Aa |
この段階で、答えはイと決まります。
(4)・(5)の解説
(4)の答えは、DNAです。
(5)については、無性生殖では体細胞分裂によって子が作られるため、その子は親と全く同じ遺伝子を持つことになります。
よって、答えはウです。
2015・神奈川・問7
最後に、2015年の神奈川県の問7に挑戦してみましょう。
問題はこちらから参照できます。
(ア)の解説
しわのある種子を作るエンドウですから、卵細胞には分離の法則から遺伝子「a」のみが含まれます。
このエンドウと種子が丸である純系のエンドウを確実に受粉させるには、しわのある種子を作るエンドウの自家受粉を防ぐ必要があります。
よって、しわのある種子のエンドウの「おしべのやく」を取り除いておかなければなりません。
答えは、3となります。
(イ)の解説
繰り返しになりますが、AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1となります。
この比より、「AA」または「aa」をもつ個体は、得られた種子全体の50%となります。
よって、答えは4となります。
(ウ)の解説
いま、QとRのどちらが「AA」で、どちらが「Aa」なのかを議論しています。
また、「AA」と「Aa」をかけあわせると、すべて種子は丸くなります。
そのため、QとRをかけあわせれば種子はすべて丸くなり、Xには2, YにはPが入ることが分かります。
「aa」と「Aa」をかけあわせると、以下の表ができ、しわのある種子が生まれることが分かります。
| A | a | |
| a | Aa | aa |
| a | Aa | aa |
また、「aa」と「AA」をかけあわせるとその子は必ず種子が丸くなるため、Zには「しわのある種子が生じる」が入ります。
(エ)の解説
茶色の毛をもつ個体の遺伝子のペアは「BB」または「Bb」です。
また、黒色の毛をもつ個体の遺伝子のペアは「bb」であることが分かります。
このとき、親のどちらも遺伝子「b」を持っていないと、「bb」をもつ個体は産まれてこないことになります。
一方遺伝子「B」に関して、仮に「Bb」と「bb」をかけあわせると、遺伝子「B」をもつ個体が産まれることになります。
よって、遺伝子「B」は少なくともどちらの親がもっていれば十分です。
以上より、(あ)には1が、(い)には3が入ります。
公立高校対策におすすめの問題集
公立高校に向け、日々の学習で活用できる書籍をご紹介します。
ステップアップ式で学習を進めたい方には、「ハイクラス徹底問題集」がおすすめです。
定期テスト対策も行える問題集でもあり、その上のレベルが公立高校レベルとなっているので、
日々の学習で入試で求められる応用力を身につけるのに最適な書籍です。
まとめ:[高校入試]理科「遺伝」の実際に出題された問題を解説!
いかがでしたか。
今回の記事では、実際に出題された「遺伝」の問題を解説しました。
割とパターンが決まっている問題でもあるので、上でご紹介した書籍を活用しつつ、今回の内容を身につくまで繰り返し解けば十分かと思います。
次回は、難関校でよく出題される「独立の法則」について解説していきます。
ご一読いただきありがとうございました。
また、本記事と合わせて以下の記事も是非ご覧ください。
![[高校入試]理科「遺伝」の実際に出題された問題を解説!](https://i0.wp.com/you-can-blog.com/wp-content/uploads/2022/06/pea-flower-g8b6bd9d38_1920.jpg?fit=1920%2C1903&ssl=1)














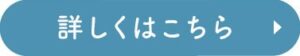
コメント