みなさんこんにちは、ゆーきゃんです。
以前の記事で、「柱状図」の問題の解き方を解説しました。
今回はその解き方を踏まえて、実際に出題された入試問題に挑戦してみたいと思います。
ここまでできれば「柱状図」に関しては完璧です!
ですので、これまでの学習の総仕上げとして「柱状図」の入試問題に挑戦してみましょう。
2021・千葉・大問2(4)
まずは、2021年の千葉県の大問2(4)に挑戦してみましょう。
問題はこちらから参照できます。
解説
それでは、解説に入りましょう。
まずは定石通り、「かぎ層」を見つけましょう。
この問題では、火山灰層があるので、かぎ層は火山灰層ということになります。
続いて、各地点の柱状図を標高を基準として書きかえていきます。
以下に各地点の「標高」・「火山灰層の上面の地表からの深さ」および「その上面の標高」をまとめてみます。
| 標高[m] | 火山灰層の上面の 地表からの深さ[m] | 火山灰層の上面の標高[m] | |
| 地点W | 105 | 20 | 105-20=85 |
| 地点X | 110 | 15 | 110-15=95 |
| 地点Y | 95 | 10 | 95-10=85 |
| 地点Z | 90 | 5 | 90-5=85 |
この表から、地点Xの火山灰層の上面の標高が他の3つよりずれており、断層によって上方向に10[m]ずれているといえます。
2018・静岡・大問4(2)
続いて、2018年の静岡県の大問4(2)に取り組んでみましょう。
問題はこちらから参照できます。
①の解説
まず、①の解説です。
れき・砂・泥に関しては以下のことをおさえておきましょう。
ですので、れき→砂→泥の順に層が積み重なっていきます。
答えは、オとなります。
②の解説
この問題でも「かぎ層」を発見することから始めましょう。
各柱状図に火山灰層があるので、これをかぎ層とします。
続いて、各地点の柱状図を標高を基準として書きかえていきます。
以下に各地点の「標高」・「火山灰層の上面の地表からの深さ」および「その上面の標高」をまとめてみます。
| 標高[m] | 火山灰層の上面の 地表からの深さ[m] | 火山灰層の上面の標高[m] | |
| A地点 | 50 | 10 | 50-10=40 |
| B地点 | 45 | 10 | 45-10=35 |
| C地点 | 50 | 15 | 50-15=35 |
いま、B地点とC地点における火山灰層の上面の標高がそろっているので、
B地点とC地点における地層は水平に積み重なっていることが分かります。
よって、答えはウです。
2020・兵庫・大問Ⅳ-1
最後に、2020年の兵庫県の大問Ⅳ-1を解説します。
一筋縄ではいかない難しい問題ですが、挑戦してみてください。
問題はこちらから参照できます。
(1)の解説
Zでは下かられき→砂→泥の順に堆積していきます。
れきは水深の浅い場所、泥は水深の深い場所に堆積されるため、水面が高くなっていったので、
この地域は沈降したことが分かります。
また、水深が深くなっていったため、海岸から遠ざかっていったといえます。
よって、答えはアです。
ここで、以下のことを覚えておきましょう。
(2)の解説
この問題でも「かぎ層」に注目しましょう。
火山灰層がありますので、これをかぎ層に利用します。
Yは火山灰層の下にあるため、まずこれが堆積されたと考えられます。
次に、Xの方がZよりも上に位置しているため、Y→Z→Xの順で堆積したと分かります。
よって、答えはエです。
(3)の解説
以下の表に地点C以外の「方角」・「標高」・「火山灰層上面の地表からの深さ」・「火山灰層の上面の地表からの高さ」および「火山灰層上面の標高」を示します。
| 方角 | 標高[m] | 火山灰層上面の 地表からの深さ[m] | 火山灰層の上面の 地表からの高さ[m] | 火山灰層の上面の 標高[m] | |
| 地点A | 北・東 | 18 | – | 1 | 18+1=19 |
| 地点B | 南・東 | 17 | – | 2 | 17+2=19 |
| 地点D | 北・西 | 20 | 3 | – | 20-3=17 |
地点AとBではその標高がそろっているので、南北方向には地層は水平に積み重なっています。
地点AとDを比較すると、東西方向では地層が傾いており、西の方が低くなっていることが分かります。
よって、答えはイです。
(4)の解説
(3)より、地点CとDで観測される地層は水平となっています。
地点Dにおいて、火山灰層の上面の標高は17[m]でしたから、地点Cにおけるその標高も17[m]となります。
地点Cの標高は19[m]であるため、その地表から2[m]下に火山灰層の上面があることになります。
以上を踏まえ、答えはウと決まります。
公立高校に向けた問題演習を行いたい方におすすめの書籍
公立高校を目指す方におすすめの問題集をご紹介します。
日々の学習から公立高校に向けた対策を行いたい場合には「ハイクラス徹底問題集」がおすすめです。
定期テスト対策も行える問題集でもあり、難易度が3段階に分かれており、無理なくステップアップできます。
そのような点からも日々の学習に最適の書籍です。
まとめ:[高校入試]実際に出題された「柱状図」の入試問題を解説!
いかがでしたか。
今回の記事では、実際に出題された「柱状図」の入試問題の解説を行いました。
実際の入試問題には見かけに差はあるものの、「かぎ層に注目し、標高基準に書きかえる」やり方が実際の入試問題でも利用できることを実感頂けたかと思います。
ご紹介した問題集や今回の記事で扱った問題を繰り返し解いてできるようになれば、怖いものはないかと思います。
是非この記事を参考にして、学習を進めていってもらえればと思います。
ご一読いただきありがとうございました。
![[高校入試]実際に出題された「柱状図」の入試問題を解説!](https://i0.wp.com/you-can-blog.com/wp-content/uploads/2022/06/mountains-gb76cfea6d_1920.jpg?fit=1920%2C1280&ssl=1)







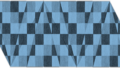





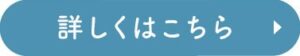
コメント